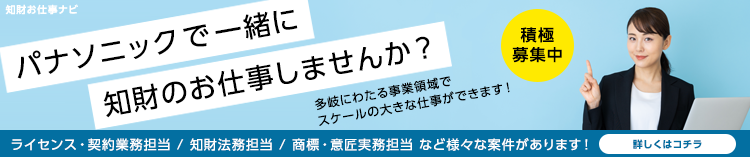この判例には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
| 審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
|---|---|---|
| 平成19ネ10097損害賠償請求控訴事件 | 判例 | 意匠 |
| 平成21ネ2110損害賠償請求控訴事件 | 判例 | 意匠 |
| 平成17行ケ10135審決取消(意匠)請求事件 | 判例 | 意匠 |
| 平成17ネ617損害賠償請求控訴事件 | 判例 | 意匠 |
| 平成22行コ10004異議申立棄却決定取消請求控訴事件 | 判例 | 意匠 |
| 関連ワード | 意匠の利用 / 意匠の創作 / 一意匠一出願(7条) / 登録意匠 / 損害賠償 / 不当利得 / 通常実施権 / 権利濫用(権利の濫用) / 実施料相当額 / 損害額 / 消滅時効 / |
|---|
| 元本PDF |
裁判所収録の全文PDFを見る
|
|---|
| 事件 |
平成
15年
(ネ)
5942号
不当利得返還等請求控訴事件
|
|---|---|
|
控訴人・被控訴人 株式会社友森鋭二郎デザイン研究所 訴訟代理人弁護士 長谷一雄 同 西浄聖子 控訴人・被控訴人 ニチハマテックス株式会社 訴訟代理人弁護士 石原金三 同 花村淑郁 同 杦田勝彦 同 石原真二 同 清水綾子 同 鈴木隆臣 同 春馬学 (以下,控訴人・被控訴人株式会社友森鋭二郎デザイン研究所を「一審原告」とい い,控訴人・被控訴人ニチハマテックス株式会社を「一審被告」という。) |
|
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
| 判決言渡日 | 2004/05/18 |
| 権利種別 | 意匠権 |
| 訴訟類型 | 民事訴訟 |
| 主文 |
一審原告の控訴及び一審被告の控訴をいずれも棄却する。 当審における訴訟費用は,全体を通じて100分し,その99を一審原告の負担とし,その余を一審被告の負担とする。 |
| 事実及び理由 | |
|---|---|
|
当事者の求めた裁判
1 一審原告 (1) 原判決の主文第2項中,1億円及びこれに対する平成15年4月9日から支払済みまでの年5分の割合による金員の支払請求を棄却した部分を取り消す。 (2) 一審被告は,一審原告に対し,1億円及びこれに対する平成15年4月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (3) 一審被告の控訴を棄却する。 (4) 訴訟費用は,第1,2審を通じて,一審被告の負担とする。 (5) 仮執行宣言 2 一審被告 (1) 原判決中一審被告敗訴部分(主文第1項)を取り消す。 (2) 上記部分に係る一審原告の請求を棄却する。 (3) 一審原告の控訴を棄却する。 (4) 訴訟費用は,第1,2審を通じて,一審原告の負担とする。 |
|
|
事案の概要等
1 一審被告(平成13年9月以前の商号は,三井木材工業株式会社である。)は,一審原告に対し,窯業系外壁材の新商品開発に関する業務を委託し(以下「本件契約」という。契約書の体裁は,覚書(甲第1号証)である。以下「本件覚書」という。),一審原告は,これに基づき,外壁材の意匠(デザイン)の製作,個々の商品の名称(ネーム)の考案等をして,その成果物を一審被告に提出した。一審被告は,それに基づき,商品(建物外装材)を作り,販売した。 本件契約の契約期間は,昭和63年8月1日から平成元年7月31日までの1年間であり,この間の委託料(月50万円,合計600万円)は全額支払済みである。 2 一審原告は,一審被告に対し,本件契約に関連して,不当利得の返還及び不法行為に基づく損害の賠償並びにこれらについての遅延損害金の支払を求めて(一部請求),本件訴訟を提起した。 一審原告の原審における主張の概要は,以下のとおりである。 (1) 本件契約には,一審被告が,一審原告が製作したデザインに係る権利を,当然に,自由に使用することができる,との定めはない。一審原告が製作したデザインの使用については,これに関する報酬を両当事者が協議して別途決めた上,一審原告が,改めて一審被告に対し許諾することになっていた。しかし,結局,一審原告は,一審被告に対し,デザインの使用を許諾したことはない。報酬に関する協議すらなされていない。 同様に,ネーム,ロゴマーク,エンブレム等についても,一審原告は,一審被告に対し,これらに係る権利を譲渡しておらず,これらを使用することの許諾もしていない。 一審原告は,商品カタログ及び販売促進ツール(販売員が商品のプレゼンテーション(提示,発表)を視覚的かつ効果的に行うために用いる資料)も作成し,一審被告に提出した。しかし,これについても,一審被告に対し,使用の許諾等はしていない。また,一審原告が行った実地調査・各種提案の結果の利用についても,同様である。 一審被告が,法律上の原因なく,一審原告が製作したデザイン等を利用して,平成元年4月以降,商品を製造して販売したことにより得た利益に関し,一審原告は,一審被告に対し,売上高に基づき計算した利益を不当利得として,その返還を求める。 (2) 一審被告は,一審原告に無断で,別紙のとおりの意匠(以下「本件意匠」という。)に係る登録意匠番号980677号の意匠登録(平成元年2月23日出願,平成9年2月10日登録,以下,「本件登録」といい,この登録に係る意匠権を「本件意匠権」」という。)を行った。X(一審原告の代表者である。以下「X」という。)は,その登録の移転を一審被告に求めた(東京地裁平成14年(ワ)第3640号・取下げにより終了)。しかし,一審被告は,これに応じず,そればかりか,登録料不納付により,平成14年10月に本件登録が抹消される,という事態を引き起こした。 そこで,本件意匠権を消滅させた不法行為に基づく損害賠償の支払を求める。 3 原審では,以下の点が争点となった。 (1) 法律上の原因の有無(本件契約に基づき,一審被告は一審原告の作成した成果物(本件意匠,ネーム等)に係る権利の譲渡を受けたか,あるいはそれらの使用を許諾されていたか。)。 (2) 不当利得の額 (3) 消滅時効 一審被告は,10年の消滅時効(平成5年3月31日以前に発生した債権の消滅)とともに,5年の商事債権の消滅時効(平成10年3月31日以前に発生した債権の消滅)をも主張した。 これに対し,一審原告は,商事債権の消滅時効の主張を争うとともに,一審原告は,一審被告に対し報酬の支払等を求め続けており,これに対し,一審被告は,本件意匠登録を秘匿するなどして一審原告の権利行使を妨げてきたのであるから,消滅時効を主張することは権利濫用であり許されない,と主張した。 4 原判決の理由の骨子 原判決は,不当利得16億3300万円と不法行為3490万円との合計16億6790万円の内金5億円の請求のうち,170万円を,不当利得によるものとして認めた。 その理由の骨子は,次のとおりである。 (1) 本件契約において,一審原告が製作したデザイン及びネームの使用については,別途一審原告が許諾を与え,両当事者が協議してその対価を決定することが予定されていた。 一審原告が行った実地調査の結果等の利用については,本件契約により,許諾されている。 デザイン及びネームについて,一審被告は,一審原告の許諾なしにこれを利用しており,不当利得がある。本件意匠の意匠登録をしたことについても,不当利得が成立している。 (2) 一審原告が製作した商品カタログ及び販売促進ツール(甲第7号証,32号証,第33号証の1ないし5)については,本件契約とは別に委託がされ,2000万円以上の制作費の実費の支払があったものであり,使用について許諾があったと認められる。 (3) 消滅時効の期間については,10年を採用する(商事債権の消滅時効は認めない。)。他方,一審原告の権利濫用の主張も認めない。 (4) 損害額 ア 一審被告は,その商品のうち商品名「マーキス」のものについてのみ,一審原告が製作したデザインを用いた。 イ 本件意匠に関する利得(使用と登録)は,他のデザイナーへの支払額等を考慮し,200万円と認める。 一審被告の現実の利得は,使用についての利得が一部時効により消滅していることなどを勘案して,70万円と認める。 ウ 一審被告が採用した「デューク」,「マーキス」,「カウンテス」,「メヌエット」,「フーガ」,「バロン」,「コラール」,「バラード」のネーム(以下,これらを併せて「本件ネーム」という。)の使用についての利得は,その使用期間,消滅時効が成立している部分があることなどから,100万円とする。 エ 本件意匠権を消滅させたとする不法行為については,一審被告は,そもそも登録料の支払を継続する義務を負っていない。不法行為は成立しない。 一審被告が将来使用する予定もなく,消滅による損害が発生したとも認められない。 5 当事者双方の主張は,次のとおり付加するほか,原判決の「事実及び理由」の「第2 事案の概要」記載のとおりであるから,これを引用する。 |
|
|
当審における一審原告の主張の要点
原判決は,本件契約に基づく委託業務の範囲を誤って認定し,一審被告の利得額を過小に認定している。 1 本件契約による業務委託の範囲について (1) 原判決は,一審被告が,①センチュリーボードAⅡシリーズ(以下,「被告商品」という。)の中のマーキス(以下「被告商品マーキス」という。)に本件意匠を使用した行為,②本件意匠に係る意匠登録の出願をして,本件登録を受けた行為,及び③本件ネームを使用した行為について,本件契約により許諾された行為に含まれないと判断した。この判断は,正当である。 本件契約の内容を定めた本件覚書は,使用許諾料等,デザイン等の成果物の使用を認める条件等につき,不完全,未成熟な要素を多く抱えている。これら不完全,未成熟な部分は,協議によって完全なものとして成熟することが予定されていた。しかし,結局のところ,これらの部分は,協議によって完全なものとして成熟するに至っていない。同部分が協議によって完全なものとして成熟することがないままに,一審原告が製作した成果物を一審被告が利用する行為が,本件契約により,法律上の権限に基づく,合法的なものになる,などということはあり得ない。 (2) 一審被告は,本件契約に基づき支払われた月50万円(合計600万円)の報酬が,低額ではないとして,これをもって,原判決の上記認定を批判する。しかし,本件契約の締結に当たっては,一審原告の製作した成果物を一審被告が商品化した場合,協議の上,一審被告が,一審原告に対し,月額50万円の固定費とは別に,別途成功報酬ないしロイヤリティーを支払うことが前提となっていた(甲第38号証。乙第5号証)。 この点は,一審原告が,他の企業との業務委託契約においても,実質ロイヤリティーの支払と同視し得る報酬を受けていること(甲第22号証,第23号証,第26号証),一審原告が商品開発の業務委託を受ける場合,社内の者のみならず,社外の者(デザイナー,カメラマン等)に仕事を発注して分担させており,その外注費も含めると,月50万円の固定費では経費にすら満たないことからも明らかである。 現に,一審原告は,本件契約の締結に至る過程で,数千万円の報酬が必要であると一審被告に申し入れている。一審原告が,月額50万円の支払で妥協したことはない。 600万円の報酬は,低額なものであり,本件意匠や本件ネームの使用許諾料等を含むものでないことが明らかである。 (3) 他方,原判決は,一審原告が行った各種実地調査の結果及び各種提案を一審被告が利用する行為について,「外壁材の素材,デザイン傾向,色彩傾向等についての実地調査,外壁材に関する市場分析については,被告商品の商品企画,販売促進戦略の提案等の前提となるものであり,本件契約により原告に委託された業務に含まれることは明らかである。また,被告商品のコンセプト等について提案したレポートの提出,壁材のパターン,レリーフ,テクスチャーのバリエーションを検討した資料の提出は,販売促進戦略の提案等に含まれ,本件契約により原告に委託された業務に含まれることは明らかである。」(17頁9行目~15行目),と判断している。 一審原告は,上記の実地調査等が,本件契約の締結を契機としてなされたことまで,否定するものではない。しかし,上記実地調査等を本件契約により委託された業務内容に含まれるとするのは,誤りである。 (4) 一審原告が行った作業の成果物は,新商品開発作業に関する資料(外壁材パターン・デザイン案等)(甲第12号証),ネーミング案(甲第11号証),パンフレット(甲第7号証,第32号証),販売促進ツール(甲第33号証),外壁サンプルピース,商品の色指定等,多数に上る。要するに,本件契約の対象とされている業務は,極めて広範囲かつ高度なものなのである(甲第38号証)。 そうである以上,本件覚書に直接記載のない業務は,別途ロイヤリティー支払の対象となることが明らかである。 (5) 各種実地調査の結果や各種提案という,一審原告の活動の成果物を利用する行為に対して,ロイヤリティーが支払われるとの前提があったとしても,その額は,定まったものでも,一審原告が機械的・客観的に算定できるようなものでもなく,協議により決められるべきものであった。そして,上記利用行為に対して,相当額のロイヤリティーを支払うという具体的な合意はまだ成立するに至っておらず,現に支払われてもいなかった。そうである以上,一審被告による上記各成果物を利用するという利益の保持を正当化する根拠もないことになるはずである。 本件意匠及び本件ネームを利用する行為についてと同様,一審被告の上記各行為を正当化する法的根拠もまた,なかったというべきである。 (6) 一審被告は,本件契約で定められた一審原告の活動の成果物を一審被告が使用することについて,本件覚書中にこれを制約する文言はない,と主張する。 本件覚書は,一審被告が作成したものであるから,成果物の利用について別途一審原告の許諾を要しないとするなら,一審被告がその旨の明示の条項を入れるべきであり,そのようにすることは極めて容易であった。ところが,そのような条項は入っていない。 そうである以上,成果物の利用については,結局のところ,本件契約によっては定められていない,と解するのが合理的である。 (7) 一審被告の主張は,本件契約が請負契約であることを前提とし,そうであるから,本件契約により一審原告が製作した成果物の権利は,一審被告に帰属する,というものであろう。しかし,その前提は誤っている。本件契約は,準委任契約であると解すべきである。 本件契約において,一審被告は,一審原告が製作したもの(デザイン等)が気に入らなかったり,不十分なものと判断したりすれば,その受領を拒絶することができた。また,本件契約の委託業務の内容は,定型的なものでなく,完成に要する時間も費用も,予測できるようなものではなかった。すなわち,本件契約において,委託された業務に係る成果物(デザイン等)の創出及びその引渡し自体が義務となっているものでなかったのである。 本件契約が請負契約でない以上,そこで定められている一審原告の活動に係る成果物も,当然に一審被告に帰属するということはできない。したがって,原判決が,覚書による業務の遂行と,その成果物の引渡しとを区別して,後者については本件契約で定められていないとしたのは正当である。 前記のとおり,一審被告は,600万円の報酬は低額ではない,と主張する。そうでないことについては,既に主張してきたとおりである。そもそも,この600万円の報酬が高額であるか否かは,上で述べたような,本件契約の法的評価に影響するものではない,というべきである。 2 本件契約に係る委託業務の成果物の価値(不当利得額)について (1) 原判決は,被告商品マーキスのデザイン利用について200万円,本件ネームの利用について100万円の不当利得が一審被告にあったとし,これに,消滅時効が成立している期間に対応する額等の減額事由を加味して,合計170万円の不当利得を認定した。 しかし,この額は低額にすぎる。 (2) 原判決は,被告商品マーキスのデザインの使用による利益及びその意匠登録による利益のうち,200万円(消滅時効が成立していない期間に対応する部分をこのうちの70万円としている。)とした根拠として,①一審被告が,被告商品のうち,一審原告以外の者が製作した,被告商品マーキス以外のもののデザインに係る権利を,一つ当たり200万円で取得していること,②一審原告は,一審被告に対し,本件契約の業務の対価として3500万円の支払を求めていたこと,③一審被告は,本件意匠権を,第三者に譲渡したり,通常実施権を設定して実施許諾料の支払を受けたりしていたものではないこと,等を挙げている。 (3) 原判決のこの認定は,一審原告が,一審被告に対し,本件意匠の使用を許諾する予定であったことを出発点としている。しかし,使用の許諾は,あくまで相当額の対価の支払を前提としていたものであり,それがない以上,使用を許諾することなどあり得ない。使用を許諾することを予定していたということは,不当利得における利得額の認定の出発点として,その一要素となる,という性質のものではない。 (4) 他のデザイナーに200万円を支払ったという点について,まず,そのような認定は何ら客観的な証拠に基づかず,不当なものであることを指摘する。 200万円が支払われたとする業務の内容,質及び量も,一審原告のなした業務のそれらとは全く異なる。本件の参考となるものではない(乙第28号証)。 (5) 一審原告は,一審被告から,本件意匠の登録を受ける権利を譲渡したことを確認するよう求められた際,一審被告に対し,選択肢の一つとして,3500万円の支払を確認の条件として提示した。この3500万円と,原判決が本件意匠の価値として認定した200万円との間には,大きな差がある。この点をどのように評価したのかについて,原判決は説得的な理由を述べていない。 (6) 原判決は,本件意匠についての一審被告の利得額を,その支出の削減という視点からしかとらえていない。本件ネームについての利得額についても,同様であると思われる。 一般的に,不当利得の額が,「負担帰属の原則」という言葉で語られるように,利得者が出捐を免れた部分を利得の本質とするものであるとしても,「財貨や負担の運動の法則に対する違反(例,無効の契約に基づく給付の場合)」,「財貨の帰属の法則に対する違反(例,他人の物の無権原使用の場合)」には,償還すべき利得額は,支出の節約額ではなく利得そのものの価値が問題となる。特に後者の場合,受益者が悪意又は重過失のときは,利息,損害賠償,超過利得,引渡義務も問題となる(四宮和夫著「事務管理,不当利得」)。 本件において,一審被告は,悪意で他人(一審原告)の財産を権原なく使用している。支出を免れた額がいくらであるかという見地から,償還すべき利得額を算出するのは妥当でない。デザインやネームの経済的価値そのものとして,利得額を検討すべきである。 (7) 上記のとおり,一審原告は,一審被告が,一審原告の作成したデザインを利用して製品を製造し,これを販売して得た利益額の一定割合を,不当利得の額として請求している。一審被告が,上記デザインに係る意匠権を第三者に譲渡したか,通常実施権を設定したかなどは,不当利得の額の算定には全く関係がない。 (8) 被告商品のデューク,マーキス,カウンテス,メヌエット,フーガ,バロン,バラード,コラールについて,平成4年度から平成9年度までの売上高は46億0262万5013円である(甲第66号証)。仮に,平成5年以前の売上げ(約8億5800万円)について消滅時効が成立しているとしても,約37億4000万円が,利得額の計算の基礎となる売上額になる。一審被告が被告商品の販売により得た利得は,これを基準として計算されるべきである。 (9) 一審被告は,本件ネームは,一般的な名詞にすぎない,と主張している。 商品の名前は,もともと,そのほとんどが,既存の一般名詞にすぎない。 しかし,特定の商品と結び付くことにより,市場において価値を発揮するものである。一般名詞であるからといって,価値を有しないことになるものではない。 一審原告は,その提案した商品コンセプト(商品の形態,機能を示唆する概念的情報)と一体となるものとして,本件ネームを提案したものであり,その選定において大きく貢献している。 3 カタログ及び販売促進ツールの利用による利得について (1) 原判決は,被告商品のカタログ(以下「本件カタログ」という。)及び販売促進ツール(以下「本件販売促進ツール」という。)の使用について,一審原告にこれを許諾する意思があったと認定し,したがって契約に基づく請求権のみが発生するから,不当利得返還請求権が発生する余地はない,とした。その根拠として,製作実費2000万円が支払われていること,一審原告は,その金員を全額,そのまま外注をした者に支払っていること,一審原告は,本件カタログ及び本件販売促進ツールをそのまま一審被告に渡していること,を挙げている。 (2) 本件では,一審原告による,一審被告に対する本件カタログ及び本件販売促進ツールの使用・頒布に対する許諾はあるが,その対価の取決めは全くなされていない。一審原告が,再三その協議を申し入れたにもかかわらず,一審被告は協議にすら応じなかった。 使用許諾と対価の支払は一体である。後者に関する協議の成立も現実の金員の支払もない以上,一審被告の利得を正当化するような,契約上の基礎は何ら確立していない,というべきである。原判決が,本件意匠や本件ネームの使用について,不当利得の成立を認めながら,本件カタログ及び本件販売促進ツールについてそれを認めなかったのは,矛盾している。 4 本件意匠権消滅の不法行為について (1) 原判決は,一審被告が,一審原告に対し,本件意匠権について登録料の支払を継続する義務を負っているとは認められず,登録料の不払は不法行為を構成しない,としている。 (2) 一審被告が,本件意匠権を登録したことは,一審原告の創作物を自己の排他的支配下に置こうとする窃盗類似の権利侵害であり,悪意の不法行為を構成することは明らかである。そして,このような場合,一審被告が本件意匠権について,民法697条の善管注意義務を負うことも当然である。 そして,Xが,別訴(取下げ済み)において,一審被告に対し,本件意匠権の登録の引渡しを求めたにもかかわらず,一審被告はこれを黙殺し,登録料の支払もせず,本件意匠権を消滅させているのである。 (3) 一審被告は,自己の事務として本件登録を行ったのであるから,事務管理が成立する余地はない,と主張する。 主観的に自己の事務であっても,客観的に他人の事務である以上,準事務管理として,事務管理の規定を類推適用すべきである。したがって,一審被告が,事務管理者として,管理継続義務(民法700条)を負っていることは明白である。 (4) 原判決は,平成14年10月30日以降,一審被告が被告商品マーキスの製造,販売をしておらず,また,第三者に対し,本件意匠の使用を許諾することもしておらず,それらの予定もなかったとして,本件意匠権登録の抹消による損害は発生していない,としている。 一審原告が主張しているのは,一審原告自身による本件意匠権の排他的利用可能性である。一審被告が本件意匠を利用することによる実施料相当額の支払を求めているのではない。 本件で,一審被告は,本件意匠権を破壊的に侵害したのであるから,その経済的価値に応じた損害を賠償すべきは当然である。 (5) 一審被告は,Xに対し,本件意匠権を存続させる機会を与えた,と主張している。 しかし,一審被告が,登録料を納付する意思がないことをXに通知したとしても,それをもって,本件意匠権を継続させることについて機会を与えたということはできない。そのような機会を与えたというためには,Xが本件意匠権の登録の引渡しを求めていた以上,登録移転の用意があることをまず表明すべきである。 しかし,一審被告はそのような表明をしていない。 5 一審被告の主張1(本件意匠及び本件ネームの使用許諾があったといえることについて)に対して 一審被告は,商品が売れたら対価を払うとの意思の表明が,一審被告から一審原告に対してあり,一審原告がこれを受け入れた,というのであれば,一審原告は,一審被告に対し本件意匠の使用自体は許諾したことになる,と主張する。 しかし,単なる意思の表明は,法的に意味のある意思表示といえるものではない。この表明は,対価の支払の時期,方法,金額の算定方法も明確でなく,単に一審被告の考えを述べたにとどまるものである。一審原告が,そのような表明に対し,同意ないし承諾をしたこともない。 そのような,具体的な内容もなく,一審原告が同意も承諾もしていない意思の表明に基づき,一審被告が法的権利を取得することは,あり得ないことである。 |
|
|
当審における一審被告の主張の要旨
1 本件意匠及び本件ネームの使用の許諾があったことについて 一審原告は,一審被告から,商品が売れたらロイヤリティーを支払うとの意思の表明があったとする。これは事実に反する。しかし,仮に,真実,一審被告がこのような意思の表明をし,一審原告がこれを受け入れたというのであれば,一審原告は,本件意匠及び本件ネームの使用自体は,許諾していたものというべきである。 具体的な金額又はその算定方法の定めがなかったとしても,客観的に相当な額のロイヤリティーを支払うとの合意があった以上,その合意は法的に意味のあるものである。この場合には,一審被告は,本件デザイン及び本件ネームの使用につき,契約責任を負うことはあり得ても,不当利得や不法行為による責任を負うことはあり得ない。 2 一審原告の主張1(本件契約による業務委託の範囲)に対して (1) 本件覚書は,次のように定めている。 「第1条 甲(判決注・一審被告)は乙(判決注・一審原告)に次の業務を委託する。 (イ) 窯業系外壁材の新商品開発に関する商品企画及デザイン製作,サンプルピース製作 (ロ) 販売促進戦略(カタログ,サンプル製作及び各種イベント等)の提案,指導,助言 (ハ) その他甲が依頼する事項」(甲第1号証) 本件意匠製作は,上記1条(イ)の,本件ネームの製作は(ロ)の対象となる。 (2) 原判決は,商品計画が本件契約の対象業務に含まれている,と認定している。これは,誤っている。商品計画なる文言は,本件契約のどこにもない。もっとも,上記のとおり,本件覚書には,「商品企画」という文言はある。しかし,これは抽象的な記載にすぎず,具体的な内容を持った委託事項ということはできない。 一審被告は,商品企画を既に策定しており,これを改めて一審原告に委託する必要はなかった。現にしていない。一審原告が,商品企画について何らかの業務を遂行したこともない。 本件契約で定められた委託料の額(月50万円,合計600万円)に対する評価(高いか安いか)に当たり,商品計画が委任の対象に含まれていることを前提にするのは,誤りである。 (3) 本件契約における主たる委託内容は,デザインの製作である。販売促進戦略の提案等も,これに付加される従たるものとして,委託内容となっていた。 もっとも,本件カタログ及び本件販売促進ツールの製作は,本件契約の範囲に入るものではなく,現に本件覚書とは別の委託契約に基づきなされ,その製作費は支払済みである。 本件契約の委託業務の大半は,デザイン製作であるといってよい。 (4) 一審被告が,窯業系外壁材のデザインに関し,他のデザイナーが作成した成果物に対し支払った報酬は,1デザインについて200万円であり,これに比較すると,一審原告に対し支払った報酬の総額(600万円)は相当に高額である。 採用したデザインの使用許諾料ないし譲渡対価を含むものと解しても,決して低額とはいえない。 本件契約締結時においては,一審原告の製作したデザイン等を,一審被告が採用するかどうか,いくつ採用するかが不確定であり,その譲渡ないし使用の対価をあらかじめ定めることが困難であったとしても,別途譲渡ないし使用許諾に関する定めをせず,すべて込みで定額の報酬を支払う契約条項を設けることは,何ら不自然でも不合理でもない。 本件契約の締結に当たり,一審被告の支払うべき対価は,一審原告の要望により,成功報酬を支払う(デザイン採用分ごとにその対価を支払う)という形のものではなく,定額報酬を支払うという形のものになったものである。この定額報酬が,製作されたデザイン等の使用料も含むものと解するのに,何の差し支えもないはずである。 (5) 本件契約において,一審原告が製作したデザイン等を一審被告が使用することについて,一審原告の許諾を得ることを要するとの明示の規定はない。その他にも,一審被告の使用を制約する特段の規定はない。 本件契約のような内容の契約では,一審被告は,採用したデザイン等を使用することが,当然の前提となっている。当事者間では,改めて使用許諾や意匠権の譲渡を受けたり,それらに対する対価を支払う必要などないと考えられていたのである。 (6) 一審原告は,一審被告が本件意匠及び本件ネームを使用したことを認識しながら,これに対して異議を述べたことはない。 (7) 以上のとおりであるから,一審被告が,本件契約により,一審原告が作成したデザイン及びネームを使用することは,当然許されていると解すべきである。 (8) 一審原告は,本件契約が準委任契約であるから,成果物の帰属は定められていない,と主張している。 仮に準委任契約であったとしても,成果物の創出が契約上の義務となることは当然である。しかも,準委任契約であるからといって,論理的に当然に,その成果物が委任者に帰属しないことになる,というわけのものではない。 3 一審原告の主張2(本件契約に係る委託業務の成果物の価値(不当利得額)の認定)に対して (1) 一審原告が主張する業務のうち,色指定は,カタログに使用するロゴやエンブレムの色の指定である。被告商品自体に対するものではない。 (2) 一審原告が,一審被告に対し提案し,一審被告が採用したデザインは,被告商品マーキスに係るものだけである。 (3) 一審原告は,単に一般名詞を分類・整理した複数のネーム案を提示しただけである。しかも,その中から,本件ネームを選定したのは一審被告である。ネームの製作に対する一審原告の作業内容は,さして重要性のあるものではない。 4 一審原告の主張3(本件カタログ及び本件販売促進ツールの利用による利得)に対して 本件カタログ及び本件販売促進ツールに対する製作は,本件契約とは別の委託契約に基づきなされたものであり,その製作実費及び報酬も支払済みである。 一審原告は,10年以上も,本件カタログ及び本件販売促進ツールの製作に関する対価の支払を請求していない。このことからも,一審原告自身,この対価はすべて支払済みであると認識していたことが明らかである。 5 一審原告の主張4(本件意匠権を消滅させた不法行為)に対して (1) 一審被告は,自己のものとして,本件意匠権を登録したものである。事務管理が成立する余地はない。 (2) 一審被告は,Xに対し,平成14年(ワ)第3640号事件の答弁書において,本件意匠権の登録料を納付しないことを通知し,一審原告が登録料を納付して本件意匠権を存続させる機会を与えた。にもかかわらず,一審原告は必要な措置を採らなかった。 |
|
|
当裁判所の判断
当裁判所も,一審被告に対する一審原告の請求は,原判決の認容した限度で理由があり,その余は理由がない,と判断する。その理由は,次のとおり付加するほか,原判決の「第3 当裁判所の判断」のとおりであるから,これを引用する。 1 当審における一審被告の主張1(本件意匠及び本件ネームの使用の許諾の存在)について (1) 一審被告のこの主張は,商品が売れたらロイヤリティーを支払うとの表明が一審被告からなされ,これを一審原告が受け入れたことを前提とする。 この点について,前者の表明があったことについては,Xの陳述書(甲第38号証等)に,これに符合する記載がある。また,A(一審原告の取引先である株式会社盛栄堂印刷所の専務取締役)の供述書(甲第42号証)には,「私(判決注・A)が,「御社の経費はどうするのですか。」と尋ねたところ,X氏は「うちの経費は必要ないですよ。センチュリーボードAⅡシリーズは,必ず爆発的に売れ,そうすれば,三井木材から成功報酬やロイヤリティーが入る約束になっています。」(2頁18行目~22行目)との陳述があり,これらからは,上記のような表明があり,かつ,これに対して一審原告が同意していたようにもみえる。しかし,反対趣旨のB(本件契約成立の前後にかけて一審被告営業本部営業促進部第一課長であった者,以下「B」という。)の陳述書(乙第24号証)の記載(一審被告は,委任製作されたデザイン等は当然に自己に帰属するものと考えており,一審原告に対しても,そのことを前提に行動したことなどが記載されている。これに関する他の証拠として,甲第2号証の1及び2参照。)に照らし,上記表明もこれに対する同意も,あったと認めることはできない。他に,これらの存在を認めるに足りる証拠はない。 (2) 一審原告(具体的には,その代表者であるX)が,自己の活動の成果物が一審被告の商品に利用され,商品が売れた場合に成功報酬ないしロイヤリティーが支払われることを期待し予定していたとしても,あるいは,一審被告が本件意匠及び本件ネームを使用すること自体に対し異議を述べていなかったとしても,それだけで,一審原告が,最終的に,本件意匠及び本件ネームの使用を許諾したことになるものではない。 一審被告が本件意匠に係る登録を受ける権利の譲渡証書に捺印するよう求めたのに対し,一審原告が,最初から拒絶するのではなく,捺印はしつつ,一定の額の金銭の支払を条件として提示している(甲第3号証の1及び2)ことからすれば,一審原告は,本件意匠及び本件ネームを一審被告に使用させ,販売実績が上がった後に,それに基づく報酬を得るという予定であったということまでは,推認することができる。しかし,結局のところ,一審原告の提示した上記条件についての協議は成立しないままに,本件訴訟に至っていることに照らすと,法律上,一審被告の本件意匠及び本件ネームの使用に対し,一審原告が確定的に許諾を与えたとまで認めることはできない,というべきである。そして,当事者が,契約の締結や紛争の話合いによる解決の過程でなした,種々の申し出・提案等について,それらを個別に切り出して独立した合意と認めることが当然に許されるものではないことはいうまでもないところである(そう解さないと,円滑な協議等がおよそできなくなるおそれがある。)。そうすると,一審原告は,あくまで,一審被告による本件意匠の使用を,一定の額の金員の支払に懸からしめていたということになるのであり,本件意匠の使用と金員の支払は,法律上一体のものとして把握されるべきであるから,結局,一審原告と一審被告の間には合意が成立せず,後者から前者に対する一定額の金員の支払がなされなかった以上,事実上黙認されていた(あるいは,後に合意が成立することを解除条件として許諾されていた)一審被告による本件意匠の利用行為は,合意不成立が確定することにより,さかのぼって法律上の原因のないものとなることになるのである。 以上のとおりであるから,一審被告の主張1は,採用できない。 2 一審原告がした実地調査の結果,提案の利用(一審原告の主張1)について (1) 原判決は,「外壁材の素材,デザイン傾向,色彩傾向等についての実地調査,外壁材に関する市場分析については,被告商品の商品企画,販売促進戦略等の前提となるものであり,本件契約により原告に委託された業務に含まれることは明らかである。」(17頁9行目~12行目),としている。この認定に何ら誤りはない。 上記のような実地調査・市場分析の結果が,最終的に窯業系外壁材という商品のデザイン・ネーミングの製作ないし決定や,販売戦略の策定という形で結実していくべきものであることは明らかである(逆にいえば,一審原告は,それらに直接役立つように実地調査・市場分析をしていったものと認める。)。これらと独立して,実地調査・市場分析の成果物の価値を論じる必要はない。 (2) 続けて,原判決は「被告商品のコンセプト等について提案したレポートの提出,壁材のパターン,レリーフ,テクスチャーのバリエーションを検討した資料の提出は,販売促進戦略の提案等に含まれ,本件契約により原告に委託された業務に含まれることは明らかである。」(17頁12行目~15行目),としている。 この認定も正しい。 もっとも,商品は,デザインやネームがよければ,それだけで当然によく売れるというものではないから,商品の販売促進戦略は,商品のデザインやネームと密接に関連するものであるとしても,なお,それら自体とは独立した価値を有すると認めることができる。しかし,原判決が挙げているレポートや資料は,なお,主として商品のデザインに極めて密接に関連するものであるから,その観点からも,それと独立して,上記レポートないし資料の作成に対する対価を支払う必要はないということができる。 (3) 以上のとおりであるから,各種実地調査・市場分析に対して,別途対価を支払う必要があると認めることはできない。一審原告の主張は,この点において既に失当である。 3 不当利得の額の計算(一審原告の主張2)について (1) 一審原告の主張は,被告商品の販売による利益を基準に,その一定の割合(被告商品マーキスについては20パーセント,その他の被告商品については10パーセント)をもって,すなわち実施料算定の方法ないしこれに類似する方法で,本件意匠及び本件ネームの価額を算定すべきである,とするものである。 市場における商品の成功(高い売上高)は,独り意匠や標章だけでなく,商品自体の特長,投下資本,宣伝,営業等が相まって達成されるものである。例えば,ある商品が,品質において競合製品に比較して優れているわけでもなく,宣伝や営業活動も取り立ててなされていないのにもかかわらず,デザインが評価されてよく売れたような場合は,当該デザインの貢献度を高く評価してもよい,といえよう。しかし,一審原告の主張する20パーセントや10パーセントという数字は,これを客観的に根拠付ける具体的な主張も証拠もない。被告商品がよく売れ,利益を上げたという結果は,本件意匠及び本件ネームだけでなく,被告商品の窯業系外壁材としての特徴(耐火性,ノンアスベスト(石綿の不使用),遮音性,断熱性等)や,その開発・生産のために投下した資本,宣伝・営業努力にも起因していることは明らかである。被告商品の売上げによる利益は,本件意匠や本件ネームの価値そのものでないことはもちろん,これから生じた果実ないし利息ということもできない。 実施料率の相場という観点からみても,甲第6号証の1及び2(「技術取引とロイヤルティ」社団法人発明協会)のように,8.1パーセントないし15パーセントという,実施料率の高率化を指摘する文献もあれば,同文献中の他の部分には,平均値はこれよりずっと低いことを述べる記載もある(乙第25号証)。さらに,甲第49号証(「実施料率」〔第4版〕・社団法人発明協会)及び乙第26号証(「ライセンス契約実務ハンドブック」社団法人発明協会)にも,ロイヤリティーの平均値が,10パーセントより低いことが示されている。 結局,一審原告の主張する10パーセント,20パーセントという実施料率はもちろんのこと,これ以下のいかなる率についても,客観的に認定することを可能にする証拠は存在しないという以外にない。 (2) 本件において,一審被告が本件意匠及び本件ネームを使用すること自体は確定的に許諾されており,その対価は,具体的には定まっていなかったものの,売上高に基づき協議して決める,との法的合意があった,と認めることはできない(もしそうであるなら,たとい具体的な対価の額ないしその算定方法の定めがなかったとしても,一審被告の使用自体には法律上の根拠があることになる。この場合には,契約上の責任はともかく,少なくとも不当利得は生じていない,という以外にない。)。一審被告が,本件意匠及び本件ネームを使用して上げた現実の利益を基準として,それらの使用による利得を算定するという方法を採用すべき必然性はない。 本件意匠や本件ネームの経済的価値そのものをもって,一審被告の利得額を算出すべきである,とする一審原告の主張自体は是認できる。しかし,本件において,他社がデザインした意匠の対価の額(これは,乙第27号証等により認めることができる。)をもって,本件意匠の経済的価値(価額)などとした原判決の判断に,誤りがあるとは認められない。 4 一審原告が提案したデザインが採用された商品(一審原告の主張2)について (1) 一審原告は,被告商品マーキス以外の商品も,一審原告が提案したデザインを採用している,と主張している。 (2) しかし,この主張を認めるに足りる証拠はない。 この点,X自身,「デザインスケッチの控えをとっておりませんので,証拠としてこれを提案することはできません。」と述べ,少なくとも直接的な証拠がないことを認めるとともに(甲第58号証の陳述書10頁2行目~3行目),甲第12号証,甲第44号証,甲第45号証から,「原告会社が多数に渡るデザインスケッチを提出したことが間接的に理解されるはずです。」と述べるにとどまっている(同10頁6行目~7行目)。一審原告が多数のスケッチを提出したことは認められるものの,そのことから,被告商品マーキス以外のデザインがそのまま,あるいは大きな変更を受けることなく,採用されたことまで認定することはできない。 甲第65号証の陳述書で,Xは,より具体的に,甲第12号証の⑨の写真の右下のものがカウンテスに,同号証の⑭の「地層」のものがフーガに,それぞれそっくりであると述べている。しかし,そのようには認められない。 5 本件ネームの価値(一審被告の主張2)について 一審被告は,一審原告がしたのは,一般名詞を分類・整理したネーム案の提示だけであり,これにさしたる価値はない,と主張し,これに対して一審原告は反論している。 本件ネームが,もともと一般名詞であることはそのとおりである。しかし,それらを,窯業系外壁材の新規商品にふさわしく,需要者に好印象を与えるようなもので,かつシリーズをなすようなものとして提案することが,一定の創作性や,一般的な需要者の意識に対する洞察力等を必要とするものであることは,明らかである。したがって,最終的な選定を一審被告が行ったものであるとしても,そのための候補案の作成を,重要性のないものということはできない。 6 本件カタログ及び本件販売促進ツールの利用による利得(一審原告の主張3)について (1) 一審原告の主張は,要するに,本件カタログ及び本件販売促進ツールについても,製作に要した実費しか支払われておらず,報酬の支払がないのであるから,本件意匠や本件ネームと同様,その使用の許諾はなされていないと認定されるべきであるとし,これに反する原判決の判断には矛盾がある,とするものである。 (2) しかし,一審原告自身,本件カタログ及び本件販売促進ツールの使用自体の許諾はあったとしているものと認められる(一審原告の控訴理由書11頁23行目~24行目)。また,明示の許諾がなかったとしても,なお,一審原告は,確定的にそれらの使用を許諾する意思を有しており,黙示の許諾があったと認めることができる。その理由は,以下のとおりである。 本件意匠及び本件ネームに係る権利の譲渡や使用の許諾を,一審原告が認めていないの理由の一つは,売上高に比例した報酬,少なくとも600万円をはるかに超える報酬の支払を希望し,これと許諾を一体のものとして考えていたからである,と認められる(甲第2号証の1,2及び第3号証の1,2等)。しかし,本件カタログ及び本件販売促進ツールについては,このような事情(何らかの条件を提示していたこと)を認めるに足りる証拠はない。本件カタログや本件販売促進ツールの使用について,一審原告が格別異議を述べたと認めるに足りる証拠もない。 前記のAの陳述書(甲第42号証)の陳述内容からは,Xは,一審被告に対し本件意匠及び本件ネームの使用を事実上させてしまい,被告商品の販売による利益を上げさせてから,報酬を得ることも視野に入れていたと推測できる。そうすると,最終的かつ決定的な交渉材料となる,本件意匠や本件ネームに係る権利の譲渡や,それらの使用許諾については,一審原告は極めて慎重な態度をとっていたと認められるものの,被告商品の販売を促進させることのできる資料を,一審被告が使用すること自体は,さほど重要視していなかったと考えるのが合理的である。 (3) したがって,本件カタログ及び本件販売促進ツールについては,一審原告は一審被告がそれらを使用することを,明示的ではないにせよ,黙示で認めていた,というべきである。 不当利得が成立しないとした原判決の判断は,正当である。 7 本件意匠権消滅の不法行為(一審原告の主張4)について (1) 一審被告は,本件意匠の創作者をXとして出願しているものの,Xに対し,本件意匠に係る登録を受ける権利を譲渡したことの確認を求めている(甲第2号証の1及び2,甲第3号証の1及び2)ものであって,譲渡を求めているものではない。 以上からは,客観的な本件契約の解釈はどうであれ,一審被告は,自己の事務であると認識して,本件出願を行ったものと認めることができる。そうすると,一審被告は,一審原告のために,本件意匠の登録という事務の管理を始めたものとは認められないから(本件意匠権が消滅するまでの間に,一審原告のために管理すると表明した事実も認められない。),事務管理が成立する余地はなく,一審被告が,登録料を納める義務を一審原告に対し負っていたと認めることもできない。したがって,管理義務を怠ったことに基づく不法行為も成立しない。 一審原告は,一審被告による本件登録は窃盗類似の権利侵害であり,悪意の違法行為である,と主張する。そうであると認められないことは,前記のとおりである。また,仮にそうであるとするなら,本件登録自体について不法行為が成立するとしても,本件意匠権を消滅させたこと自体について,不法行為が成立するとは認められない。 また,一審原告は,本件のような場合にも事務管理の規定の類推適用を認めるべきである,とする。しかし,上記事実関係の下では,不当利得の規定(原物返還ができない場合)を適用することができるか否かは別として,事務管理の規定を適用ないし類推適用する余地はないというべきである。 一審原告の主張は,採用できない。 (2) 一審被告は,平成14年(ワ)第3640号事件の答弁書において,「なお,本件意匠登録にかかる平成14年2月11日以降の登録料につき,被告はその支払をしておらず,かつ,その支払の意思はないことを念のため申し述べる。」と陳述している。 確かに,一審被告は,本件登録の移転そのものを認めたものではない。しかし,前記のとおり,一審被告に登録料の支払を継続する等の管理義務はないことからは,一審被告は,Xが本件意匠権を存続させるために必要な申し出はした,というべきである。このことからも,本件意匠権を消滅させたことについて不法行為が成立するということはできない,というべきである。 (3) 一審原告は,一審原告自身が,本件意匠権の排他的利用ができなくなったことによる損害を主張しているのであって,本件意匠権の実施料相当額の支払を求めているのではないから,被告商品マーキスの製造,販売,第三者に対する許諾をしておらず,その予定もなかったことなど無関係であり,そのことを理由に損害は発生していない,とした原判決には誤りがある,と主張する。 この点に関し検討すべきは,本件意匠権が消滅したため,それを排他的に利用する権利を一審原告が行使し得なくなったことに基づく損害の額である。一審原告の主張は,この点を指摘するものとしては正しい。 しかし,原判決が認定した事実に加え,被告商品マーキスの売上げが顕著に落ちていること(平成4年度1億5000万円から平成9年度35万円・甲第66号証)からは,将来において,本件意匠を使用した商品(窯業系外壁材)を販売しようとする者が出現するとの蓋然性を認めることは困難である。そうすると,一審原告が本件意匠を排他的に使用するか,そうでないかとの間で,その使用により一審原告が得る利益に,有意的な差が生じるとまでは認めることができない(競合品がなければ,当然である。)。一審原告は,効果的な販売戦略を用いて,本件意匠を用いた窯業系外壁材をヒット商品とすることができ,そうなれば競合品が現れるといいたいのであろう。しかし,そのような事態が相当程度の蓋然性をもって発生するとは認められない。 損害の発生を認めなかった原判決の判断は,相当である。 (4) したがって,不法行為を根拠として,本件意匠権の消滅に基づく損害の賠償を請求する一審原告の主張は,採用できない。 8 結論 以上検討したところによれば,原判決は相当であって,一審原告の控訴及び一審被告の控訴はいずれも理由がないことが明らかである。そこで,これらをいずれも棄却することとし,当審における訴訟費用の負担について民事訴訟法67条,61条を適用して,主文のとおり判決する。 |
| 裁判長裁判官 | 山下和明 |
|---|---|
| 裁判官 | 設樂隆一 |
| 裁判官 | 高瀬順久 |